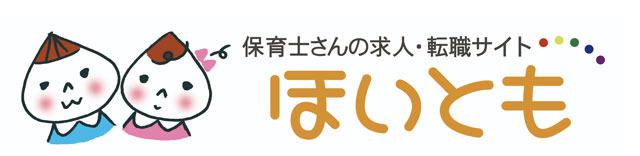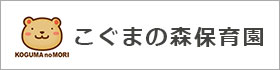2025.07.02
お役立ち情報
夏こそ注意!保育園でのノロウイルス・ロタウイルス対策!

先月、京都のホテルで修学旅行生100人以上が集団食中毒というニュースが取りざたされました。また大阪市の6月の感染症週報でも、感染性胃腸炎が発生件数の1位でした。子どもたちが密に接する保育園では感染のリスクが高くなります。激しい下痢や嘔吐、腹痛、発熱などの症状に加え、夏は下痢・嘔吐に伴う脱水症状も心配です。正しい知識と効果的な対策を、いま一度、確認しておきましょう。
正しい知識を持っておくことが大切です
細菌やウイルスによって起こる胃腸の炎症をひっくるめて「感染性胃腸炎」といいます。これに対してアレルギーやフグ・キノコの毒などが原因のものを「非感染性胃腸炎」といいます。そして胃腸炎の中で飲食物を介して発症するのが、いわゆる「食中毒」です。
感染性胃腸炎には主に「細菌性」と「ウイルス性」の2つがあります。細菌とはO-157で知られる出血性大腸菌、サルモネラ菌、黄色ブドウ球菌など。最近はカンピロバクター、ウエルシュ菌などもよく耳にしますね。加熱が不十分な肉や魚介を口にすることで発症しますが、生肉を切った包丁、魚介を触った手から他の食品への「二次汚染」も少なくありません。
ウイルスには、ノロ、ロタ、アデノなどの種類があります。ウイルス性は冬に多いと思われがちですが、大阪では6月から多くの発症例が報告されています。暑さで体力・免疫力が低下する夏場こそ油断は禁物。こちらも元々はカキや二枚貝に存在するといわれますが、原因食品が特定されることは稀。感染者が触った調理器具やタオルなどを介することが多く、糞便や嘔吐物から感染が広がることもあります。
保育園でできるのは、まず徹底した手洗い
子どもたちは何でも手でさわります。何かをさわった手をすぐに口に持っていきます。だから感染者がふれたあらゆる物から感染が広がります。これを防ぐには第一に手洗いの徹底。まずは子どもたちに手洗いのタイミングや正しい手順を教えましょう。
タイミングとしては食事の前後、トイレの後、友だちとたくさん接触したあとなど。洗い方は(1)十分な量の石鹸を手に取って手のひら・指の間・爪の中・手首まで丁寧に洗う、(2)少なくても20秒は手をこするように洗い続ける、(3)流水で石鹸を完全に洗い流して清潔なタオルやエアドライヤーで乾燥させる、という流れです。手順がビジュアル的に分かる掲示物や、楽しい手洗い歌を取り入れるのも有効です。
もちろん保育士も同様です。食事の前後、トイレ後のほか、オムツを交換したあと、子どもたちと接触したあとなどは、子どもたち以上に手洗いを徹底しましょう。
ノロやロタにはアルコール消毒液が効かない
アルコール60%以上、エタノール70%以上なら効果があるともいわれますが、スーパーの入り口などに設置されている一般的なアルコール消毒液は30%程度ですし、高濃度のものは子どもの肌には刺激が強すぎます。そこで有効なのが次亜塩素酸系の消毒液です。次亜塩素酸ナトリウム水溶液はエンベロープもカプシドも透過するので、両方のウイルスの内部を不活性化できます。園児がよく触るところも、定期的に次亜塩素酸系で消毒すると効果的ですよ。
また保育園では子どもの嘔吐物の拭き残しが乾燥・粉塵化して感染が広がることも知られています。子どもは日常的によく嘔吐します。その処理には普段から注意が必要です。まず対応する保育士は必ずマスクとゴム手袋をつけること。拭き残しに気をつけ、最後に床を徹底的に消毒すること。ここではキッチンハイターなどの塩素系漂白剤(次亜塩素酸ナトリウムを含んでいて強力です)を薄めて使うのがオススメです。
万が一、感染者が出たら迅速な初期対応を!
O-157などの一部を除き、感染性胃腸炎は「法定伝染病」ではないので、水痘などのように「出席停止期間」がありません。症状さえ回復すれば登園できることになっています。仕事の都合をつけて子どもを家で看ないといけない保護者には丁寧で安心感を与える説明が必要です。場合によっては病後保育の利用をお勧めしたり、登園の可否については医療機関への相談を促したり…。大人にも感染しますので、家庭内でも消毒などが必要なことを伝えましょう。
どれだけ対策をしても100%防ぐことは不可能です。万が一、感染者が出たら適切な「初期対応」が何より重要。感染をそれ以上拡大させないことに気持ちを切り替え、落ち着いて行動しましょうね。
短大の幼児教育学科を卒業後、兵庫県で私立幼稚園での幼稚園教諭からスタート。その後、大阪府北摂の公立保育所と私立認可保育所で保育士として勤務。豊富な保育経験・スキルを有する。現在は、保育学生や保育士が安心して働ける環境を実現する活動を株式会社ワークプロジェクトで実践。保育ポリシーは「保育の正解はこどもが決める」。