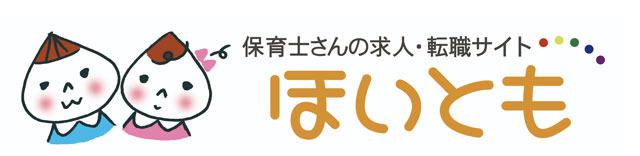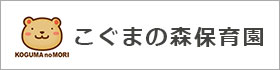2025.08.06
転職コラム
連載インタビュー(2)福井先生に聞く:園長から何度も注意、保護者から苦情…保育士としてどう対処?

梅花女子大学の福井先生のインタビュー、2回目は注意・叱責・クレームなどへの対処方法です。園長から何度も注意される。保護者からクレームを受ける。保育園ではよくあることですが、そんなとき受け流すのか、謝るのか、反論するのか…。心理学を研究されている先生ならどうするかを、かなり突っ込んでお聞きしました。
【福井 斉(ひとし)先生プロフィール】
◇梅花女子大学 心理こども学部 心理学科 准教授 ◇社会学博士
研究テーマは「子どもの自尊感情を高める取り組み」。趣味はアニメ鑑賞。熱烈な阪神タイガースファンで「阪神を応援し続けるファン心理をライフワークとして研究していきたい」とも。
注意された日の翌朝って気まずい
◇ほいとも
例えば園長や主任から何度も注意を受けた次の日、どんな顔で、どんなことばで挨拶すればいいでしょうか?
◆福井先生
「昨日はすいませんでした」ですね。
◇ほいとも
まず謝るということですね。ちなみに先生も上席から注意を受けることがあるんですか?
◆福井先生
あります、あります。「また君か!」ってね(笑)。注意を受けたときは何はともあれ「すいません」と謝りますね。「本当に反省してるのか」と疑われたとしても、注意してくれるのは、気にかけてくれている証拠。逆に注意されなくなったら「ヤバいな」と思います。そこは嗅ぎ分けられると思います。
◇ほいとも
それでもまたお小言が始まったら、回避策はありますか?
◆福井先生
「以後、気をつけます」ですね。もっというと「ありがとうございます。以後、気をつけます」かな。気持ちとしては「わかってるから、それ以上いわないで」という感じで、フェードアウトを試みると思います。
例えば園長や主任から何度も注意を受けた次の日、どんな顔で、どんなことばで挨拶すればいいでしょうか?
◆福井先生
「昨日はすいませんでした」ですね。
◇ほいとも
まず謝るということですね。ちなみに先生も上席から注意を受けることがあるんですか?
◆福井先生
あります、あります。「また君か!」ってね(笑)。注意を受けたときは何はともあれ「すいません」と謝りますね。「本当に反省してるのか」と疑われたとしても、注意してくれるのは、気にかけてくれている証拠。逆に注意されなくなったら「ヤバいな」と思います。そこは嗅ぎ分けられると思います。
◇ほいとも
それでもまたお小言が始まったら、回避策はありますか?
◆福井先生
「以後、気をつけます」ですね。もっというと「ありがとうございます。以後、気をつけます」かな。気持ちとしては「わかってるから、それ以上いわないで」という感じで、フェードアウトを試みると思います。
逆に注意する立場になったら
◇ほいとも
保育園では上から注意されることもありますが、後輩を注意しなきゃいけないこともあります。
先生も学生さんを注意されることがありますか?
◆福井先生
もちろん、ありますよ。
◇ほいとも
何度も注意していると気まずくなったり、話しづらくなったりするんですが、そんなときはどう声をかけられますか?
◆福井先生
「元気か?」ですね。さらに様子を見てしんどそう、へこんでそうと感じたら「大丈夫か?」と尋ねます。ふだんから学生にはよく声をかけるほうですが、それは相手を極力知りたいという思いからなんです。なので「いまの状態」を把握する努力をしますね。
◇ほいとも
なるほど。「大丈夫?」に対する返事で相手の心情を知るということですね。
◆福井先生
そうです。いまの状態や気持ちがわかれば、あとはそこに寄り添って話ができますからね。
保育園では上から注意されることもありますが、後輩を注意しなきゃいけないこともあります。
先生も学生さんを注意されることがありますか?
◆福井先生
もちろん、ありますよ。
◇ほいとも
何度も注意していると気まずくなったり、話しづらくなったりするんですが、そんなときはどう声をかけられますか?
◆福井先生
「元気か?」ですね。さらに様子を見てしんどそう、へこんでそうと感じたら「大丈夫か?」と尋ねます。ふだんから学生にはよく声をかけるほうですが、それは相手を極力知りたいという思いからなんです。なので「いまの状態」を把握する努力をしますね。
◇ほいとも
なるほど。「大丈夫?」に対する返事で相手の心情を知るということですね。
◆福井先生
そうです。いまの状態や気持ちがわかれば、あとはそこに寄り添って話ができますからね。
「失敗」って防げる?
◇ほいとも
注意するにしてもされるにしても、そこには「失敗」という原因があると思います。そもそも「失敗」って心理学的にはどういうことなんでしょうか?
◆福井先生
何回も同じようなことで失敗するということは、何らかのつまずきがあるんですよ。その課題に対しての向き合い方とか苦手意識とか、個々人で特性めいたものがあるんだと思います。なので教える立場なら、特性的な部分を理解した上で指導や注意をしますね。
◇ほいとも
逆に先生はご自身の失敗について、どう考え、どう対策されていますか?
◆福井先生
その事柄のレッドラインを知っておくことです。例えば僕は提出期限を守るのが苦手なんですが、「いつまでなら待ってもらえるか」の期限だけは超えないようにしてます。「また福井くんか…」といわれることも多いんですが、何回も遅れると、もう次は誘ってもらえないとか、チームから外されるとかになっちゃいますよね。だからレッドラインだけは超えないようにすることですね。
◇ほいとも
相手の失敗も、自分の失敗も、まず苦手なことやつまずきを知って対策を講じるんですね!
注意するにしてもされるにしても、そこには「失敗」という原因があると思います。そもそも「失敗」って心理学的にはどういうことなんでしょうか?
◆福井先生
何回も同じようなことで失敗するということは、何らかのつまずきがあるんですよ。その課題に対しての向き合い方とか苦手意識とか、個々人で特性めいたものがあるんだと思います。なので教える立場なら、特性的な部分を理解した上で指導や注意をしますね。
◇ほいとも
逆に先生はご自身の失敗について、どう考え、どう対策されていますか?
◆福井先生
その事柄のレッドラインを知っておくことです。例えば僕は提出期限を守るのが苦手なんですが、「いつまでなら待ってもらえるか」の期限だけは超えないようにしてます。「また福井くんか…」といわれることも多いんですが、何回も遅れると、もう次は誘ってもらえないとか、チームから外されるとかになっちゃいますよね。だからレッドラインだけは超えないようにすることですね。
◇ほいとも
相手の失敗も、自分の失敗も、まず苦手なことやつまずきを知って対策を講じるんですね!
座れば怒りもおさまる
◇ほいとも
保育園では園長や主任のほか、保護者から苦情を受けることもよくあります。いい対処法があれば教えてください。
◆福井先生
苦情をいってくる相手にはガス抜きが必要。対策としては、とりあえず相手の話を聞くことです。僕なら5分、10分と相手の話を聞き続けますね。聞いているうちに反論したくなるかもしれないけど、怒っている相手は聞く耳を持っていません。まずはひたすら聞きますね。
◇ほいとも
でも黙って聞いていると、どんどん加熱して話が止まらない方もいて…
◆福井先生
そういう人は軽く20〜30分は話し続けますよね。僕だったら「ちょっとこちらで続きを伺います」と場所を移して、必ず座って話します。大事なのは立ったままで話を聞かないということです。
◇ほいとも
必ず座る? それはどうしてですか?
◆福井先生
人は座ると攻撃行動がおさまる傾向があるんです。お互いが立つからぶつかるんですね。どちらかが座っていれば、「コラー!」みたいな声は出ないんですよ。座るという行動はクールダウンにつながります。座りながら怒り続けるって、結構難しいんですよ。
そういえば園長からのお小言も、保護者からの苦情も、ほとんどが「立ち話」だったかも。早くその場をやり過ごしたくて「座る」なんて考えもしませんでした。それに「注意される=気にかけてくれている」「苦手意識やつまずきを知れば失敗を回避できる」というのも新しい気づきでした。これからは注意されるときも、するときも、ちょっと心持ちが変わりそうです。
※聞き手:ほいとも・上嶋幹子
保育園では園長や主任のほか、保護者から苦情を受けることもよくあります。いい対処法があれば教えてください。
◆福井先生
苦情をいってくる相手にはガス抜きが必要。対策としては、とりあえず相手の話を聞くことです。僕なら5分、10分と相手の話を聞き続けますね。聞いているうちに反論したくなるかもしれないけど、怒っている相手は聞く耳を持っていません。まずはひたすら聞きますね。
◇ほいとも
でも黙って聞いていると、どんどん加熱して話が止まらない方もいて…
◆福井先生
そういう人は軽く20〜30分は話し続けますよね。僕だったら「ちょっとこちらで続きを伺います」と場所を移して、必ず座って話します。大事なのは立ったままで話を聞かないということです。
◇ほいとも
必ず座る? それはどうしてですか?
◆福井先生
人は座ると攻撃行動がおさまる傾向があるんです。お互いが立つからぶつかるんですね。どちらかが座っていれば、「コラー!」みたいな声は出ないんですよ。座るという行動はクールダウンにつながります。座りながら怒り続けるって、結構難しいんですよ。
そういえば園長からのお小言も、保護者からの苦情も、ほとんどが「立ち話」だったかも。早くその場をやり過ごしたくて「座る」なんて考えもしませんでした。それに「注意される=気にかけてくれている」「苦手意識やつまずきを知れば失敗を回避できる」というのも新しい気づきでした。これからは注意されるときも、するときも、ちょっと心持ちが変わりそうです。
※聞き手:ほいとも・上嶋幹子

■インタビュアー・監修/上嶋幹子
短大の幼児教育学科を卒業後、兵庫県で私立幼稚園での幼稚園教諭からスタート。その後、大阪府北摂の公立保育所と私立認可保育所で保育士として勤務。豊富な保育経験・スキルを有する。現在は、保育学生や保育士が安心して働ける環境を実現する活動を株式会社ワークプロジェクトで実践。保育ポリシーは「保育の正解はこどもが決める」。
短大の幼児教育学科を卒業後、兵庫県で私立幼稚園での幼稚園教諭からスタート。その後、大阪府北摂の公立保育所と私立認可保育所で保育士として勤務。豊富な保育経験・スキルを有する。現在は、保育学生や保育士が安心して働ける環境を実現する活動を株式会社ワークプロジェクトで実践。保育ポリシーは「保育の正解はこどもが決める」。