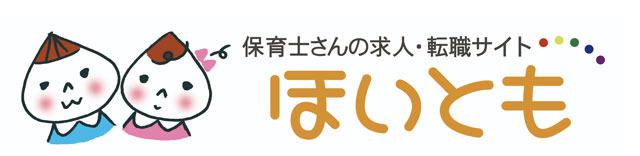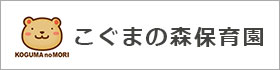2025.08.20
お役立ち情報
保育園の行事、準備がめんどうにならないために 〜運動会編〜

みなさんの園では秋の運動会の準備、もう進めていますか。「ゼロからテーマを考えるのがめんどう」「とにかく準備がたいへん」というのは正直な声だと思います。そんなときは基本に立ち返りましょう。運動会の意義や目的、園やクラスの保育方針を思い起こせば、やるべきことが見えてくるはずです。みなさんの「めんどう」を少しでも解消するため、今回は「年齢別の演目・競技例」も紹介しちゃいます。
運動会は「体験型学習のクライマックス」
運動会は走る・跳ぶ・投げるといった動きを通じて筋力や心肺機能を発達させるだけでなく、順番待ちなどの社会ルールを理解したり、仲間を応援するなどの共感性を身につけたりする場でもあります。さらに保護者が子どもの成長を実感し、家庭と園の連携を深めるハブとしても機能します。
また最近の保育所保育指針(2018年改定)や幼児期運動指針(2021年改訂)では、「遊びを中心とした身体活動の質と量の確保」「子どもの主体性を高める環境構成」が重視され、運動会を年間カリキュラムと連動した<体験型学習のクライマックス>と位置づける傾向にあります。
テーマ決めは園やクラスの保育目標に沿って
まずは文科省の指針を理解すること。次に園の保育方針やクラスの保育目標を再確認すること。例えばクラス目標が「いきいきと活動する」「みんなと力を合わせて」などであれば、きっと普段から目標に沿った活動をしているはずで、運動会もその延長線上にあります。新年度に保護者にお知らせしたクラス目標の達成具合を見てもらう場。そう考えれば、ほら、テーマの方向性が見えてきませんか?
0〜2歳児は、かくれんぼ、ふれあい体操、かけっこ
0~2歳はつかまり立ち、歩行などの粗大運動の習得期。よちよちと歩き回るだけで微笑ましいですね。そこに手を振る動作や投げて拾う動作などを加えると体の成長も伺えます。例えば…
◆大好きな曲でふれあい体操
保護者と一緒に体を動かします。無理に振り付けを決めず自由にやれば、子どもたちは跳んだり、手を振ったり、リラックスして得意な動き・好きな動きを見せてくれます。
◆かくれんぼ
1~2歳児はかくれんぼも大好き。ひょっこり出てくる動作は愛らしく、保育士の指示で隠れたり、出てきたり、集まったりする姿からは成長も感じられるはず。
◆かけっこ
無理なく走れる短い直線で。「保護者がゴールで待っている」式にすれば、子どもたちの緊張もほぐれます。
3〜5歳児は、みんなでダンス、本格競技も
◆みんなでダンス
曲に合わせて旗やポンポンを振るなど、同じ振り付けで動きます。ぴったり合ったときは全員が達成感を味わえます。
◆デカパン競争、おんぶ競争
どちらも主に3歳児向け、保護者と一緒に楽しめる「親子競技」。ただ張り切り過ぎるお父さん・お母さんもいますので、ケガしないように注意が必要です。
◆玉入れ、リレー
4~5歳になると競争や力試しをしたくなり、玉入れ、かけっこ、リレーなどの本格的な競技にも一生懸命になります。もちろん勝ち負けを伴いますが、子どもたちにとっては「負けて悔しい」も貴重な体験。また何回やってもおもしろい競技なら、勝ち負けに関係なく本気で楽しめるはずです。
毎回大好評の「どの手・どの足がウチの子?」
例えば段ボールをつい立てにして、子どもたちの足だけを見せる。段ボールに空けた穴から手だけを出す。段ボールには事前に子どもたちと一緒に絵を描いて、足を土から生えた野菜に見立てたり、手を夜空の星に見立てたり、工夫次第で年次に関係なく楽しめます。「さわってもOK」なので我が子との、時にはヨソの子とのスキンシップにもなりますよ。
保護者からは毎回、「足だけだと自分の子って分からなかった」「手をマジマジみることがなかった」「運動会の後、子どもの体をよく観察するようになった」などの感想が寄せられます。
水分補給などの熱中症対策も不可欠です
運動会は子どもたちの成長を確認できる大切な行事。そして保育士がたいへんな準備をして開催する一大イベント。事故なく楽しい一日にしたいですね。
短大の幼児教育学科を卒業後、兵庫県で私立幼稚園での幼稚園教諭からスタート。その後、大阪府北摂の公立保育所と私立認可保育所で保育士として勤務。豊富な保育経験・スキルを有する。現在は、保育学生や保育士が安心して働ける環境を実現する活動を株式会社ワークプロジェクトで実践。保育ポリシーは「保育の正解はこどもが決める」。