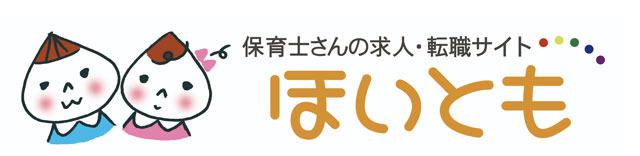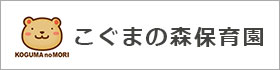2025.08.27
お役立ち情報
子どもたちの夏バテ、保育園でやるべき予防&改善対策を徹底解説!

35度を超える猛暑日は当たり前。最低気温が27〜28度なんていう超熱帯夜も続いています。こうなると夏バテは避けて通れません。特に子どもたちは夏バテしているという自覚がなく、自分で何かに気をつけることもできません。ここは保育士としての真価を発揮するタイミング!忙しい保育現場でも無理なく取り入れられる夏バテ対策、子どもたちの元気と笑顔を守る実践ノウハウを徹底的に解説します。
【症状1】食欲不振・体力の低下
何だか食欲がない。いつものように体が動かない。これ、夏バテの典型的な症状ですね。子どもの食欲不振の主因は自律神経の乱れによる胃腸血流の低下です。高温下では自律神経より交感神経が優位に働き、消化器の動きが抑制されて空腹を感じにくくなる。食欲がないからと冷たいアイスや飲み物ばかりを摂ると胃粘膜が冷え、さらに胃腸の働きが弱くなる。食べないから当然、体力も落ちる。そんな悪循環が生じます。
ただ子どもたちは「先生、ぼく夏バテっぽい」なんていえません。逆に顔色だけで「この子、夏バテ」と判断するのも困難。そこで、①主食完食率が2日続けて7割未満、②園庭遊びで15分以内に「休みたい」という、③昼寝が平常より30分以上長い…といった簡易スクリーニングの基準を設けておくことをオススメします。
【症状2】睡眠不足・イライラなどの情緒不安定
睡眠の大半は夜ですが、昼に短時間でもぐっすり眠れるとスッキリすることがありますね。だから保育園での午睡環境づくりが重要。遮光カーテンで室内照度を200ルクス以下に。サーキュレーターで空気を循環。冷感シーツや薄手のガーゼケットで発汗による寝苦しさを抑制。これで午睡の質が上がるはずです。
【症状3】免疫や抵抗力の低下
例えば「口内炎が治りにくい」「鼻水が水様から粘性に変わる」「微熱が数日続く」などは免疫力低下の黄信号。小さな異変を見逃さず、気づいたらこまめな体温測定と記録を徹底しましょう。
<対策1>水分補給は「多め」「ぬるめ」で
ただしキンキンに冷えた水は消化機能を鈍らせ、食欲不振や腹痛を招きかねません。また市販のスポーツドリンクは大量の糖分・塩分(ナトリウム)を含みます。500mlで角砂糖15個分といわれる糖分は肥満や虫歯の原因に、ナトリウム過多は腎臓の負担になります。「おいしくな〜い」と不評でも、常温の水や白湯がベストです。
<対策2>「鶏ささみそうめん」などバランスの取れた食事を
でも食欲のない夏にしっかり食べさせるのは難しいですよね。そこで完食率抜群、夏の人気メニューを紹介します。焼き鮭フレーク+枝豆+刻み海苔の「和風だしの冷やし茶漬け」、レモン香る「鶏ささみそうめん」、野菜たっぷり「豚肉みそ冷しゃぶ」。3つとも喉ごしがよく、ビタミンB1とCもたっぷり。ほとんどの子がペロっといっちゃいますので、ぜひ試してみてください。
<対策3>家庭と連携して規則正しい生活習慣を
生活サイクルは家庭によって様々ですが、「子どものため」という気持ちは同じです。保護者には就寝リズムを整えるために、①就寝1時間前にテレビ・タブレットを消す、②入浴は就寝の90分前までに、③寝室を暗くし子どもだけで入眠できるよう声掛けを短くする…という3点を提案すると理解を得やすいですよ。
もちろん家庭との連携は睡眠以外でも重要です。園児をこまめに観察し、「いつもと感じが違うな」と思ったらまずは記録。発熱がなくても連絡帳などで様子を報告し、翌日「家庭での様子」を知らせてもらいましょう。夏バテ気味なら「家でゆっくり休ませてあげたい」と思いがちですが、家庭にはそれぞれ仕事の都合や事情があります。そういうときこそ、園でゆったりさせてあげられるといいですね。
短大の幼児教育学科を卒業後、兵庫県で私立幼稚園での幼稚園教諭からスタート。その後、大阪府北摂の公立保育所と私立認可保育所で保育士として勤務。豊富な保育経験・スキルを有する。現在は、保育学生や保育士が安心して働ける環境を実現する活動を株式会社ワークプロジェクトで実践。保育ポリシーは「保育の正解はこどもが決める」。