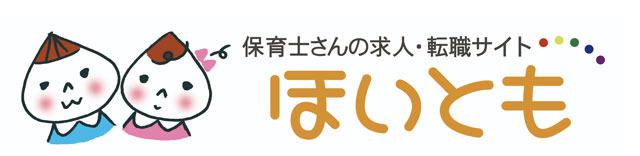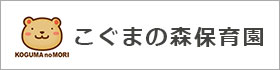2025.09.03
お役立ち情報
夜の保育園で「十五夜のお月見会」…きっと特別な経験になるはず!

♪うーさぎ、うさぎ、なにみてはねる、じゅうごやおつきさま、みてはーねる♪ わらべ歌「うさぎ うさぎ」ですね。日本には月の模様を「餅をつくうさぎ」に見立てたり、お団子を供えてお月見をしたりという素敵な文化・風習があります。夜のイベントの開催は簡単ではありませんが、今年は十五夜に「お月見会」をしてみませんか。子どもたちにとって、きっと貴重な学習体験、忘れられない思い出になるはずです。
2025年の十五夜は10月6日(月)です
月は29.4日の周期で満ち欠けが1周しますので、満月はほぼ毎月見られます。その中でも旧暦8月15日の満月の夜を「十五夜」といい、十五夜お月様を「中秋の名月」と呼びますね。今年の十五夜は10月6日(月)。見頃は全国的に18時〜21時とされています。
十五夜にお団子を供え、すすきなどを飾り、みんなで名月を愛でながら豊作を祈る。かつては日本の伝統行事でしたが、残念なことに最近はそんな風習もめっきり減ってきましたね。
お月見は日本の文化を学び、秋を感じる絶好の機会
十五夜は豊作を祈り、収穫に感謝する秋の伝統行事です。節分の鬼のお面、七夕の笹飾りなども合わせて展示すれば、日本文化を横断的に学ぶ機会にもなります。
また名月を見る、お団子を味わう、園庭の隅のコオロギの声に耳を傾ける、少し冷え始めた夜の空気を肌で感じるなど、秋を五感で受け止める絶好のチャンスにもなります。
お団子づくりから始めるのも貴重な体験
例えば子どもたちは主材料の上新粉がお米からできていることを知り、その手触りに「サラサラで雪みたい!」と目を輝かせるかもしれません。粉を練ると生地になり、丸めて蒸すと団子になるという形状の変化に驚くかもしれません。
お団子は丸い月を模して作られていること、そこに豊穣・健康・幸福の願いが込められていること、十五夜にちなんで15個供えることなども、ぜひ分かりやすくお話ししてあげてください。食べる際にはみんなで手を合わせて感謝する時間を設けると、食材の尊さ・ありがたさ、「いただきます」の意味をあらためて学べるはずです。
アレルギー・火傷・誤飲への注意も忘れずに
誤飲を防ぐために、小さめに丸めるのもポイント。もちろん、カセットコンロと蒸し器で蒸すのは大人の役目です。でも蒸す際の湯気や匂いは、ぜひ子どもたちにも共有してあげてください。米粉が蒸しあがる香り、子どもたちにとっては初体験かもしれません。
「あれ?砂糖は入れないの?」と思うかもしれませんが、最初は甘みナシで、米粉の味を知るのもいい経験になります。あとで加糖きな粉、みたらしダレをかけてあげれば、味の変化にも驚くはずです。ただしキンキンに冷えた水は消化機能を鈍らせ、食欲不振や腹痛を招きかねません。また市販のスポーツドリンクは大量の糖分・塩分(ナトリウム)を含みます。500mlで角砂糖15個分といわれる糖分は肥満や虫歯の原因に、ナトリウム過多は腎臓の負担になります。「おいしくな〜い」と不評でも、常温の水や白湯がベストです。
歌や紙芝居などで伝統文化への興味を育む
興味が湧いたら伝統をきちんと教えることも大切です。うさぎが餅をつく影絵や紙芝居を見せたり、「うさぎ うさぎ」を合唱したり…。手遊びを加えた楽しい餅つきの歌も動画で配信されていますので、気になった人はぜひチェックしてみてください。
十五夜の絵本、『おつきみおばけ』などがオススメ!
余談ですが、お月見は十五夜だけでないんです。その年の収穫に感謝する旧暦9月13日の「十三夜」、稲刈りが終わって田んぼの神様を山へ送る旧暦10月10日の「十日夜(とおかんや)」と、合わせて年3回。十五夜と十三夜、2回お月見をすることを「二夜の月」、3回コンプリートで「三月見」というそうです。さすがに保育所で3回はできせんが、十五夜に覚えたお団子づくりを、絵本『つきみだんご』を参考に、引き続き家庭で楽しんでもらうのもいいかもしれませんね。
※参考資料
『おつきみおばけ』 ◇作/せな けいこ ◇ポプラ社
『つきみだんご』 ◇作/はまの ゆか ◇光村教育図書
『うさぎさんのおもちつき』 ◇作/えむあんどえむ ◇Kindle版
短大の幼児教育学科を卒業後、兵庫県で私立幼稚園での幼稚園教諭からスタート。その後、大阪府北摂の公立保育所と私立認可保育所で保育士として勤務。豊富な保育経験・スキルを有する。現在は、保育学生や保育士が安心して働ける環境を実現する活動を株式会社ワークプロジェクトで実践。保育ポリシーは「保育の正解はこどもが決める」。