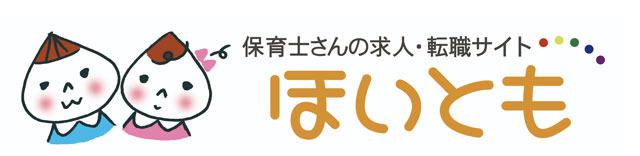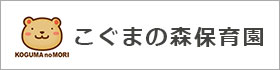2025.09.10
お役立ち情報
社会に出ると必要になる「協働性」の基礎、保育園の遊びの中でどう育む?

同じ読みで「共同」というのもありますが、最近はビジネスでも「協働」がよく使われます。例えば、チームで協働、A社とB社の協働プロジェクト、官民協働で…みたいに。力を合わせるという意味の「共同」より、ともに働く・具体的に行動するというイメージが強いからかもしれません。いまや協働性は社会人に不可欠な要素とされ、小・中学校でも「協働的な学び」が推奨される中、その基礎を保育園で身につけることも大切です。協働性を育む具体的な遊び方などを紹介していきますね。
みんなでやり遂げた喜びが、将来の問題解決能力に
「ブロックでお城、つくろう!」「僕、壁をつくる!」「じゃあ僕は屋根をつくるね!」「やったぁ、できた!」…これも立派な協働ですね。途中、ブロックの取り合いがあったかもしれません。「もう赤がない」「かわりにオレンジ使ってみたら」なんてやりとりがあったかもしれません。
小さないさかいを乗り越え、譲り合い助け合って完成させたときに、子どもたちは大きな達成感に包まれるはずです。このプロセスを経験し喜びを知ることが、将来の問題解決能力につながるんです。「大人語」でいうと、時には自分の意見も主張しながら他者を尊重し、建設的な議論を重ねてよりよい解決策を見出す、という感じですね。
協働性を育む遊び(1)「グループ活動型の遊び」
段ボールで大きな秘密基地をつくる際は、「ぼくがテープで貼るから、ちょっと支えてて」といった協力が不可欠。クラスみんなでの劇では、「もうちょっと楽しそうにしたほうがいい」「もっと大きな声で」など意見を出し合いながら、一緒に練習を重ねて完成度を高めていく。まさに協働そのものです。
協働性を育む遊び(2)「役割分担が必要な遊び」
さらに「私、どれにしようか迷ってるお客さんね」とシチュエーションを決めたり、「次は僕がお客さんになる」と役を交代したりもします。どうすればもっと面白くなるか、みんなが楽しめるかを一人ひとりが考え、アイデアを出し合ったり、話し合ったりという場面が自然に発生します。
協働性を育む遊び(3)「自然環境を活用する遊び」
また虫探しも個々に行動するのではなく、「探検隊」を結成すれば一味違ってきます。「ぼくは石の下を探すよ」「じゃあ私は葉っぱの裏!」と担当を決めたり、「この虫、図鑑で調べてみようよ」と誰かを誘ったり…。チームプレイに発展するはずです。
大縄跳び、大きな積み木などは協働性を生みやすい
こうした関わりの中で子どもたちは「みんなで一緒にやると、もっと楽しくなる」「一人でできないことも、みんなでやればできる」という成功体験を積み重ねていきます。
保育士はできるだけ口を挟まず見守りましょう
またおもちゃの取り合いなどのトラブルでも「○○ちゃんに貸してあげなさい」と指導するのではなく、「どうすればみんなで楽しく使えるかな?」と問いかけるようにしましょう。もちろん子どもたちだけで解決できない、これ以上は危険と判断したら介入が必要ですが、主体性を奪わないように、子ども同士の話し合いが生まれるように、できる限り「見守る」に徹するほうがいいと思います。
そういえば保育士の仕事も典型的な協働ですね。みんなでアイデアを出し合えば、もっと楽しい運動会や発表会ができる。みんなで子どもたちを見守れば、より高い安全性を実現できる。園に関わる誰もが「保育隊」の一員ですね。
短大の幼児教育学科を卒業後、兵庫県で私立幼稚園での幼稚園教諭からスタート。その後、大阪府北摂の公立保育所と私立認可保育所で保育士として勤務。豊富な保育経験・スキルを有する。現在は、保育学生や保育士が安心して働ける環境を実現する活動を株式会社ワークプロジェクトで実践。保育ポリシーは「保育の正解はこどもが決める」。