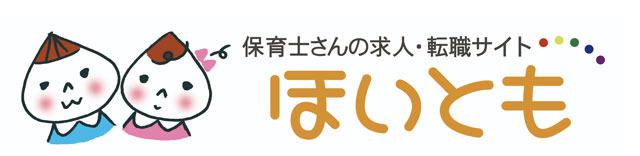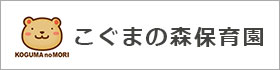2025.09.17
お役立ち情報
先輩保育士に学ぶ!秋の行事の準備、ストレスゼロで進める裏ワザ!

運動会、発表会、ハロウィン、遠足、クリスマスと、9〜12月は行事がいっぱい。子どもたちに喜んでもらいたい。保護者の期待に応えたい。通常業務も忙しいけど頑張らなきゃ。そんな気持ちで全行事の準備に全力を注いだらストレスも溜まりますね。だったら最初から、できる限り「ストレスゼロ」を目指しませんか。そんな方法ある? あるんです! 先輩保育士がそのコツやポイントをこっそり教えてくれました。
まずは重要度と緊急度をもとに優先順位づけ!
【K保育園/T先生(保育士歴11年)】
運動会、ハロウィン、遠足の準備を同時並行で進めるのはたいへん。ぜんぶ完璧にしようとして負担が増えて、かえって行事の質が落ちるなんてこともありますね。まず何をやればいいのかを「優先順位づけ」すると、かなり気も楽になりますよ。
その基準になるのが重要度と緊急度です。例えば運動会なら、プログラム決めは重要度も緊急度も高め。これが決まらないと何も進まないので、最優先でやります。飾りつけは重要度高めだけど緊急度は低いので、前日までにじっくり少しずつ。市販のもので済む準備は取り合いになるかもしれないので緊急度は高めだけど、買えばいいだけなので重要度は低めです。
優先順位づけをすれば、何からやればいいのか、どこに力を入れればいいのかが明確になって、無駄なく効率的に準備を進められますよ。
運動会の旗には、ふだん子どもたちが描いた絵を活用!
飾りつけの旗も、わざわざ運動会用にあらためて作る必要はないと思います。たとえば自由時間に子どもたちが描いた絵を貯めておいて、それをこっそり旗にすると「私の絵が旗になってる!」「あれ、僕の絵だ!」とみんな大喜びです。
白い紙に描いた絵も、うぐいす色・えんじ色などの台紙に貼り付けるとクッキリ映えます。まだ絵が描けない乳児には旗の台紙にスタンプで模様をつけてもらいます。これ、子どもたちが楽しそうにペタペタしてるうちに、何枚でもできちゃうんですよね。
ハロウィンの衣装は発表会にも使い回し!
衣装はカラーポリ袋や不織布などで作りますが、1回きりで捨てちゃうのはもったいないと思って、ハロウィンの衣装を発表会にも使うことにしました。衣装に合わせて台本を調整する必要はありましたが、製作の手間を大幅に省けました。
カラーポリ袋ですから破れることもあります。でも手直ししているうちに、子どもたちも愛着が湧いてくるようでした。ウチではハロウィンで使ったお菓子カゴも、発表会の小道具に使い回しました。物を大事にする気持ちも育ちますし、ちょっとエコにも貢献です。
運動会の競技も、遠足のお弁当も「固定」してしまう!
ウチでは運動会の年齢別の競技を固定してます。3歳は親子おんぶ競走、4歳は玉入れ、5歳は徒競走という具合です。毎年一から考える必要がありませんし、子どもたちも保護者のみなさんも「来年は徒競走ね」と逆に楽しみにしてくれてます。
さらに秋の遠足ではお弁当を「おにぎり」に固定してます。おかずは中に握り込んでラップに包むだけ。お弁当箱を広げる必要も、箸やフォークを使う必要もなし。準備も、食べる時間も、片付けも減らせます。保護者の方にも「お弁当に悩まなくていい」と好評なんです。
ストレッチやいい香りなどで、自分をリフレッシュ!
準備で忙しくて睡眠時間が減ったりすると、余計にストレスが溜まりますよね。だから手軽に済ませられることは簡単にやっちゃうことにしています。例えば料理をしないでお惣菜やインスタント物を活用するとか、情報収集はスマホで効率的にやるとか。
ちょっとしんどいなって思うときは深呼吸や軽いストレッチも効きますよ。私は仕事中でも遠慮なくやってます。家に帰ったら好きなアロマを焚いたり、お風呂あがりにいい香りのハンドクリームを使ったり、数分ほど目をつむって頭を休めたり…。とにかく疲れてたら、いい準備はできません。自分に合ったリフレッシュ法、リラックスタイムを見つけて習慣化するといいみたいです。
園全体でも、ぜひ負担軽減に向けた取り組みを!
若い保育士ほど「子どもや保護者のために行事を成功させなきゃ」と準備に一生懸命です。もちろん悪いことではないんですが、仕事量や気持ちが限界を超えて辞めてしまう人もたくさん見てきました。個々の頑張りに頼らず、園全体で負担軽減に取り組むことが必要です。
ウチでは職員会議などで定期的に行事や準備、業務フローなどを話し合う機会を設けています。例えば「この準備を省けないか」「行事を簡素化できないか」から始まり、ときには「そもそもこの行事は本当に必要か」という話になったりもします。
「この作業が面倒」「これに時間がかかる」といった不満を遠慮なくいい合うと「ガス抜き」にもなりますし、そこから建設的な議論に発展して実際に行事を見直したことも少なくありません。みなさんの園でも、ぜひやってみてくださいね。
短大の幼児教育学科を卒業後、兵庫県で私立幼稚園での幼稚園教諭からスタート。その後、大阪府北摂の公立保育所と私立認可保育所で保育士として勤務。豊富な保育経験・スキルを有する。現在は、保育学生や保育士が安心して働ける環境を実現する活動を株式会社ワークプロジェクトで実践。保育ポリシーは「保育の正解はこどもが決める」。