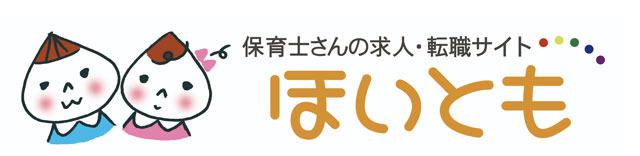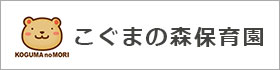2025.10.22
お役立ち情報
園児も大好き「秋のお散歩」、楽しさ倍増の2ヶ条・安全第一の3ヶ条件って?

子どもたちは園外へのお散歩が大好きです。安全対策には気を遣いますが、保育士にもいい気分転換になりますね。特に気候も穏やかで自然も豊かな秋は絶好の季節。もちろん近くの公園に行って遊ぶだけでも子どもたちは大喜びですが、ちょっとした工夫で楽しさが倍増します。もちろん楽しむためには安全が大前提。今回は楽しさアップ、安全性アップのポイントをまとめて紹介します。
【楽しさ倍増・その1】落ち葉、どんぐり、秋の自然をフル活用!
青く高い空、爽やかな風、金木犀の甘い香り、コオロギの声…。秋のお散歩では五感で季節を体験できます。でも子どもたちがいちばん好きなのは、触って集めて楽しむ秋。色とりどの落ち葉や、様々などんぐり、これを利用しない手はありません。
例えば落ち葉は、たくさん繋げてネックレスや冠を作ることができます。園に持ち帰って画用紙に貼ったり、スタンプとして使うこともできます。
どんぐりは「宝物集め」にぴったり。「僕のほうが大きい!」「これ、へんなカタチ!」と競い合って集めるはず。小さな「ウバメガシ」、細長い「マテバシイ」、丸くて大きい「クヌギ」など、図鑑を持っていけば種類も学べます。持ち帰ればコマやヤジロベエにもなるスグレモノですね。
【楽しさ倍増・その2】お散歩マップづくりで地域への関心度アップ
園に戻ったら、みんなで歩いた道を思い出しながら、大きな紙に地図を描いてみましょう。そして印象に残った場所、見つけた虫や花などを、絵やことばで書き込んでいきましょう。保育士がスマホで撮った写真をプリントアウトして貼るのも、持ち帰った落ち葉を飾るのもアリですね。
「あそこに○○屋さんがあった!」「ここにキレイな花が咲いてた!」「この公園に大きなすべり台があった!」など、子どもたちからいろんな声が上がるはず。それを一枚にまとめれば「みんなの地図」が完成し、町や地域への関心も高まりますよ。
【安全第一・その1】まずはコースの選定と徹底した下見
下見では「子ども目線」を意識しましょう。子どもの目の高さにある枝、子どもの足だとはまってしまいそうな側溝のフタのすき間なども見逃さないように。また放置されたゴミ、落ちているガラス片など、子どもたちが思わず触ってしまいそうな危険物にも要注意です。
もちろん切れない枝や撤去できない物もありますが、事前に知っておけば、その数メートル手前で子どもたちに注意を促すことができますね。
【安全第一・その2】交通ルールの徹底、保育士同士の連携
ただ基本行動が形骸化してしまわないように「渡る前には必ず立ち止まる」「車が来ていないかよく見る」「運転手と目を合わせるように」など、実践的な行動を分かりやすいことばで指導しましょう。
保育士同士が声や合図、アイコンタクトで連携を取ることも重要です。先頭の保育士は前方の安全確認。後方の保育士は遅れがちな子や体調の変化に注意。中間の保育士は全体のバランスを取る。役割分担とチームワークで子どもたちの安全を守りましょう。
【安全第一・その3】ケガや体調不良、トラブルの発生も想定して
ケガや体調不良なら、まずその子どもを安全な場所に誘導→症状により消毒や水分補給など必要な処置を→速やかに園に状況報告→その後の指示を仰ぐ。不審者に出会った際は、まず子どもたちを安全な場所に避難させる→同時に大きな声で助けを求める→すぐに警察に連絡。そんな流れや役割を決めておけば、いざという時も慌てません。
110番・119番に通報する際は、現在地、発生した事案、ケガ人の有無や人数、事故の状況や不審者の特徴などを、落ち着いて正確かつ迅速に伝える必要があります。これも日頃からシミュレーションし、きちんと心構えをしておきたいですね。
さぁ準備万端!秋のお散歩へ!
準備が整ったら、さぁ出発!坂道やデコボコ砂利道を歩くことで、子どもたちはバランス感覚や運動能力を高めます。年下の子と手をつなぎ足並みをそろえて歩くことで、思いやりや協調性も育まれます。地域の方と「こんにちは」と挨拶を交わすことで社会とのつながり、コミュニケーション能力も培われます。
でもやっぱり、子どもたちが喜ぶのがいちばん。今日はどこで、どんな秋を楽しむか。寒くなる前にどんどん出かけちゃいましょう!
短大の幼児教育学科を卒業後、兵庫県で私立幼稚園での幼稚園教諭からスタート。その後、大阪府北摂の公立保育所と私立認可保育所で保育士として勤務。豊富な保育経験・スキルを有する。現在は、保育学生や保育士が安心して働ける環境を実現する活動を株式会社ワークプロジェクトで実践。保育ポリシーは「保育の正解はこどもが決める」。