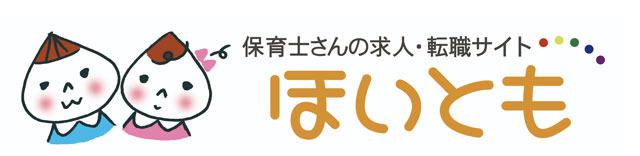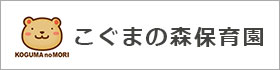2025.11.12
お役立ち情報
保育士の悩みもコレで解決!子どもたちが全集中する絵本読み聞かせの極意!

前回は秋冬のオススメ絵本を紹介しました。いい絵本が見つかったら、さぁ子どもたちに読み聞かせてあげましょう。「でも園児が集中してくれない」「読み方に自信がない」「もっと子どもたちを惹きつけたいけど方法がわからない」といった声もよく耳にします。そこで今回は園児の心をつかむ「読み聞かせの極意」を伝授します!
まずは準備が大事!座る位置や本の高さを工夫!
読み聞かせは準備段階から始まっています。「見えない」という不満は子どもたちの集中力を削ぐ最大の要因。全員にちゃんと絵本が見えるように工夫が必要です。
まずは保育士が要の位置になり、扇型に子どもたちを座らせましょう。年次の低い子、背が小さい子はできるだけ前にという配慮も忘れずに。
次は絵本の高さです。少人数なら子どもたちと同じ目線で床に座るのもアリですが、見やすさを考えて高めの椅子に座るほうがいいと思います。前の子の頭で遮られることもなく、保育士からも全員の表情を見渡すことができますからね。
「さぁ始まるよ!」という雰囲気づくりを!
例えば、みんなで「はじまる、はじまる♪」といった手遊び歌を歌ったり、専用のベルやマラカスを鳴らすなど「読み聞かせの合図」を決めておいたり…。
子どもたちの気持ちを読み聞かせモードに切り替え、これから始まる物語への期待感を生む演出で、集中力が高まってきたら準備完了です。
聞き取りやすい声で、間とテンポを意識して!
もう一つ大事なのが間です。ページをめくる直前の間、句読点での短い間を意識するだけで、子どもたちは「次に何が起こるんだろう」という期待で物語への没入感を深めます。
さらに場面に合わせてテンポを変えるのも効果的。嵐の「ザーザー」といった擬音語、緊迫する場面では少し早口で読むとドキドキ感が増します。静かな情景描写やお母さんのセリフはゆったり語りかけるように読むと、より穏やかさ優しさが伝わります。すると物語に臨場感が生まれ、感情移入しやすくなるんです。
余計な説明や質問、アドリブは要らない
ついついやっちゃいそうですが、逆にそれが子どもたちの集中を断ち切ることもあるので、できる限り控えたほうがいいと思います。もちろんアドリブも不要です。
解説やアドリブは保育士の理解・解釈です。絵本のことばや文章は忠実に読んで、理解や解釈は子どもたちに任せるのがいちばん。一方的なイメージの押し付けは、子どもたちの豊かな想像を邪魔することになりかねません。
集中が途切れた子には目配せや寄り添いを
それでも集中が戻らない場合は、そっとそばに寄って優しく肩に手を置いたり、その子を膝に乗せて耳元で読み聞かせたりするのも効果的です。
ポイントは一人ひとりに寄り添いながら「みんなで一緒に物語を楽しむ時間」を壊さないこと。個々を大事に、同時に全体を大事に。難しそうに感じるかもしれませんが、読み聞かせ以外の場面でも、きっとみなさんが日常的にやっていることだと思いますよ。
読後の余韻づくり、繰り返し読みも大事です!
また子どもたちは同じ本を「もう一回読んで!」とよくせがみますね。そんなときは「昨日も読んだでしょ」なんていわず、リクエストに応えてあげましょう。もう展開を知っているという安心感の中で、プロットやニュアンスをより深く理解したり、初回には気づかなかった小さな絵を発見したり…。2回目・3回目も、子どもたちは新鮮な気持ちを失いません。
ちょっと大げさに「極意」なんていいましたが、これは努力を重ねないと体得できない秘技ではありません。例えば「面白いことばの繰り返しを楽しんでほしい」「主人公の温かい気持ちに触れてほしい」など、意思を持って臨めば自然に適切な間やテンポになってくるはずです。「読み聞かせは苦手…」なんて思い込まず、まずはその絵本の魅力を再確認してみましょう!
短大の幼児教育学科を卒業後、兵庫県で私立幼稚園での幼稚園教諭からスタート。その後、大阪府北摂の公立保育所と私立認可保育所で保育士として勤務。豊富な保育経験・スキルを有する。現在は、保育学生や保育士が安心して働ける環境を実現する活動を株式会社ワークプロジェクトで実践。保育ポリシーは「保育の正解はこどもが決める」。