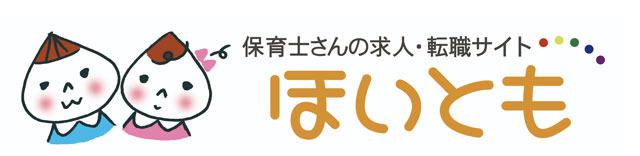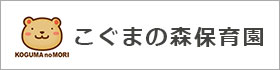2025.09.24
転職コラム
連載インタビュー第2弾(1)福井先生に聞く:転職に踏み出す人・現職に留まる人って?

またまた梅花女子大学の准教授、福井先生にインタビューの機会をいただきました。今回は「転職に踏み出せる人・踏み出せない人」についての2連載です。いま『ほいとも』では来年4月入職希望の登録者が増えています。その中には「実際に転職に踏み出す人」と「最終的に現職に留まる人」がいます。この差は何なのか。心理学の観点から解説をお願いしました。
【福井 斉(ひとし)先生プロフィール】
◇梅花女子大学 心理こども学部 心理学科 准教授 ◇社会学博士
研究テーマは「子どもの自尊感情を高める取り組み」。趣味はアニメ鑑賞。ライフワークとおっしゃる「阪神を応援し続けるファン心理の研究」も、今年のリーグ優勝でさらに加速!?
現職に留まる人って、どんな人?
◇ほいとも
先生、前回に引き続きよろしくお願いします。
◆福井先生
はい、こちらこそよろしくお願いしますね。
◇ほいとも
『ほいとも』は保育士さんの転職をお手伝いする会社で、基本的に転職希望の方が登録に来られます。もちろん「転職する方」が多いんですが、最終的に「現職に留まる方」もいらっしゃいます。この差は何でしょうか?
◆福井先生
これはDNAでも示されているんですが、日本人は全般的に「慎重な民族」なんです。だから物事を切り替えられる人より、切り替えられない人のほうが多いんです。転職はいわば新しいチャレンジで、その先はどうなるか分かりませんよね。
◇ほいとも
確かに転職はリスクも伴うっていわれますね。
◆福井先生
そうなんです。転職を考えるということは現状に何らかの問題があるはずなんですが、日本人は「我慢すればいい」という発想になりがちです。心はモヤモヤするけど、失敗したときのリスクを考えると、現状維持で自分が我慢すればいいと思っちゃう。これ、転職せずに現職に留まる人に多い傾向だと思いますね。
先生、前回に引き続きよろしくお願いします。
◆福井先生
はい、こちらこそよろしくお願いしますね。
◇ほいとも
『ほいとも』は保育士さんの転職をお手伝いする会社で、基本的に転職希望の方が登録に来られます。もちろん「転職する方」が多いんですが、最終的に「現職に留まる方」もいらっしゃいます。この差は何でしょうか?
◆福井先生
これはDNAでも示されているんですが、日本人は全般的に「慎重な民族」なんです。だから物事を切り替えられる人より、切り替えられない人のほうが多いんです。転職はいわば新しいチャレンジで、その先はどうなるか分かりませんよね。
◇ほいとも
確かに転職はリスクも伴うっていわれますね。
◆福井先生
そうなんです。転職を考えるということは現状に何らかの問題があるはずなんですが、日本人は「我慢すればいい」という発想になりがちです。心はモヤモヤするけど、失敗したときのリスクを考えると、現状維持で自分が我慢すればいいと思っちゃう。これ、転職せずに現職に留まる人に多い傾向だと思いますね。
では転職に踏み出す人は、どんな人?
◇ほいとも
逆に転職に踏み出せる人は、どんな考え方なんでしょうか?
◆福井先生
まず「自分はこうなりたい」っていうビジョンを持っていますね。そして自分がより幸せになる方法をいつも考えている。「自分らしい働き方」とか「自分に合う仕事」とかを追求できる人だと思います。
◇ほいとも
自分の幸せを最優先ってことですか?
◆福井先生
いやいや、そうじゃないんです。踏み出せる人は自分だけじゃなく、他の人の幸せも考えていますよ。まわりも幸せでないと自分も幸せにはなれない。自分だけが幸せだと何事も長続きしない。そういうこともちゃんと知っているんです。
逆に転職に踏み出せる人は、どんな考え方なんでしょうか?
◆福井先生
まず「自分はこうなりたい」っていうビジョンを持っていますね。そして自分がより幸せになる方法をいつも考えている。「自分らしい働き方」とか「自分に合う仕事」とかを追求できる人だと思います。
◇ほいとも
自分の幸せを最優先ってことですか?
◆福井先生
いやいや、そうじゃないんです。踏み出せる人は自分だけじゃなく、他の人の幸せも考えていますよ。まわりも幸せでないと自分も幸せにはなれない。自分だけが幸せだと何事も長続きしない。そういうこともちゃんと知っているんです。
留まる人にも幸せになってほしい
◇ほいとも
思い切って転職したほうが幸せになれるんでしょうか?
◆福井先生
決してそういうわけじゃないんですが、真面目な人ほど自分が我慢することを選んでしまうという傾向はありますね。
◇ほいとも
真面目だからいろいろ考えちゃうんですね。でも真面目な人にも我慢せず、幸せになってもらいたいんです。何かアドバイスはありませんか?
◆福井先生
最終的に転職するかしないかは置いておいて、まずは「自分はこうなりたい」という理想を持つことですね。そのためには自分の「強み」を知り、「自分には何ができるのか」を理解することが大事です。
◇ほいとも
「強み」を知れば、一歩を踏み出せるんでしょうか?
◆福井先生
「強み」を知ることは「自信」に繋がります。踏み出すためには、この「自信」が欠かせないんです。踏み出す=転職するってことじゃないですよ。現職に留まるにしても「自分はこれができる!」という自信を持ち、「こうなりたい!」と思って行動すれば我慢が目標に変わります。目標を成し遂げれば幸せになれます。これも「一歩を踏み出す」ことだと思いますよ。
思い切って転職したほうが幸せになれるんでしょうか?
◆福井先生
決してそういうわけじゃないんですが、真面目な人ほど自分が我慢することを選んでしまうという傾向はありますね。
◇ほいとも
真面目だからいろいろ考えちゃうんですね。でも真面目な人にも我慢せず、幸せになってもらいたいんです。何かアドバイスはありませんか?
◆福井先生
最終的に転職するかしないかは置いておいて、まずは「自分はこうなりたい」という理想を持つことですね。そのためには自分の「強み」を知り、「自分には何ができるのか」を理解することが大事です。
◇ほいとも
「強み」を知れば、一歩を踏み出せるんでしょうか?
◆福井先生
「強み」を知ることは「自信」に繋がります。踏み出すためには、この「自信」が欠かせないんです。踏み出す=転職するってことじゃないですよ。現職に留まるにしても「自分はこれができる!」という自信を持ち、「こうなりたい!」と思って行動すれば我慢が目標に変わります。目標を成し遂げれば幸せになれます。これも「一歩を踏み出す」ことだと思いますよ。
自分の「強み」って何だろう?
◇ほいとも
ちょっと考えてみたんですが、「あなたの強みは?」って聞かれても、すぐに出てきませんね。
◆福井先生
そうなんですよ。学校とかでも「自分の強み」を考えさせる機会はほとんどないですし、日本人は自分を押し出すのが苦手ですから。それはそれで欧米の人から「おくゆかしい」って評価されることもあるんですけどね。
◇ほいとも
でも「強み」を知ることが大事なんですよね?
◆福井先生
はい、そのとおり!「強み」を知ることは自分を信じること、つまり「自信」の源ですから。
◇ほいとも
その「強み」を簡単に知る方法なんて、あったりしますか?
◆福井先生
ええ、ありますよ!この機会にぜひ多くの人に知ってもらいたいですね。
保育士の強みといえば「手遊びをたくさん知っている」「ピアノが弾ける」だったりしますね。でも実際は「他の先生も手遊びのレパートリーは多いし…」「初見だと上手く弾けないこともあるし…」といった考えがよぎって、「自分だけの強みとはいえないかも」となりがちです。福井先生のおっしゃる「強み」とは何か。どうやって「強み」を簡単に知るのか。次回、さらに詳しくお聞きしていきます。
※聞き手:ほいとも・上嶋幹子
ちょっと考えてみたんですが、「あなたの強みは?」って聞かれても、すぐに出てきませんね。
◆福井先生
そうなんですよ。学校とかでも「自分の強み」を考えさせる機会はほとんどないですし、日本人は自分を押し出すのが苦手ですから。それはそれで欧米の人から「おくゆかしい」って評価されることもあるんですけどね。
◇ほいとも
でも「強み」を知ることが大事なんですよね?
◆福井先生
はい、そのとおり!「強み」を知ることは自分を信じること、つまり「自信」の源ですから。
◇ほいとも
その「強み」を簡単に知る方法なんて、あったりしますか?
◆福井先生
ええ、ありますよ!この機会にぜひ多くの人に知ってもらいたいですね。
保育士の強みといえば「手遊びをたくさん知っている」「ピアノが弾ける」だったりしますね。でも実際は「他の先生も手遊びのレパートリーは多いし…」「初見だと上手く弾けないこともあるし…」といった考えがよぎって、「自分だけの強みとはいえないかも」となりがちです。福井先生のおっしゃる「強み」とは何か。どうやって「強み」を簡単に知るのか。次回、さらに詳しくお聞きしていきます。
※聞き手:ほいとも・上嶋幹子

■インタビュアー・監修/上嶋幹子
短大の幼児教育学科を卒業後、兵庫県で私立幼稚園での幼稚園教諭からスタート。その後、大阪府北摂の公立保育所と私立認可保育所で保育士として勤務。豊富な保育経験・スキルを有する。現在は、保育学生や保育士が安心して働ける環境を実現する活動を株式会社ワークプロジェクトで実践。保育ポリシーは「保育の正解はこどもが決める」。
短大の幼児教育学科を卒業後、兵庫県で私立幼稚園での幼稚園教諭からスタート。その後、大阪府北摂の公立保育所と私立認可保育所で保育士として勤務。豊富な保育経験・スキルを有する。現在は、保育学生や保育士が安心して働ける環境を実現する活動を株式会社ワークプロジェクトで実践。保育ポリシーは「保育の正解はこどもが決める」。